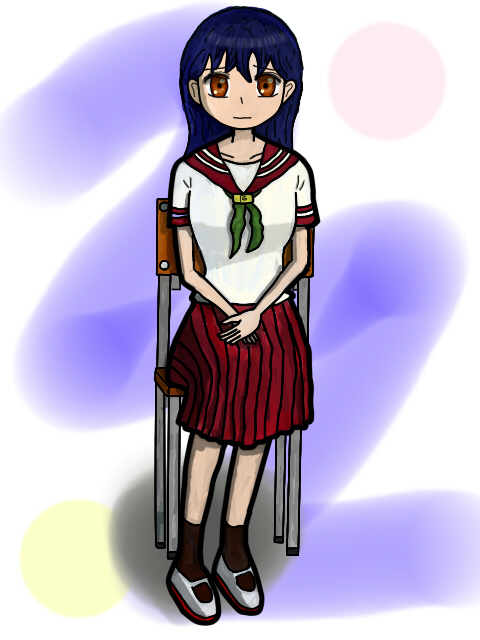名前:漆口ふたえの個人的な体験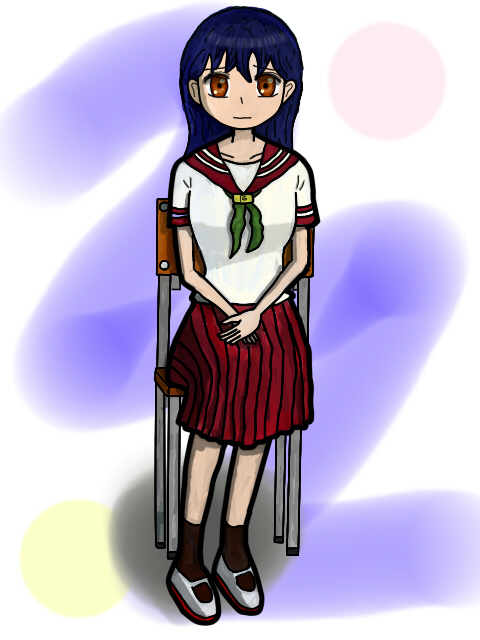
HP :5
攻撃力:0
防御力:0
素早さ:4
剣技:
・召喚剣<0/6/0/2/高高/ハンドウケイセイ>
・召喚剣<10/0/0/4/熱熱絶絶/トウソウガンボウ>
・召喚剣<5/0/0/4/熱絶衝衝熱/ドウイツシ>
・召喚剣<20/0/1/2/死盾護/タイコウ>
・召喚剣<5/0/0/2/魔魔魔魔魔魔魔/オキカエ>
・召喚剣<5/1/0/4/熱熱衝衝/ショウカ>
・召喚剣<5/0/0/3/鏡鏡鏡鏡鏡鏡/ジコトウエイ>
・召喚剣<25/0/0/2/死回4斬/トウカイ>
・召喚剣<5/5/0/2/衝衝/コウゲキ>
・召喚剣<5/1/0/4/熱熱衝絶/ヨクアツ>
・召喚剣<5/0/0/4/鏡鏡鏡鏡鏡/セッシュ>
設定:
12.
ベッドもシーツもどこまでも白いのに、なぜか清潔な気がしなかった。部屋、いやフロア全体に漂っている尿のような匂いのせいだろうか。
「ここがひとまずの漆口さんのスペースですから。もうすぐ夕飯の時間ですね。その時間になったら、食堂前にご飯のお盆が載ったラックが来るんで、自分の名前の紙が乗ってるのを取ってね。食堂で食べてもこの部屋で食べてもいいです」
「……はい」
ピピ、と脇の下に挟んだ体温計が鳴る。それを看護師に渡す。
「次は、えーと、着物ですね。はい、立って」
立ち上がり、看護師が持った病院着に体を合わせる。
「上も下もMでいいですね。それから、この紙に書いているのがが規則です。持ち込んじゃダメなのは、危険物と、コンセントを使う物と――」
看護師の説明を聴きながら、ぼんやりと今までのことを思い出していた。
フコーの言葉で死ぬことを決めた私は、台所に行って包丁を手に取った。自分の首に刃を当てたところで、母が帰ってきて私を発見した。
母の行動は俊敏だった。私に駆けよると、腕を掴みあげた。取り落とされた包丁が、鈍い音を立てて床に突き立った。誰の足にも当たらなくてよかったと思った。
何してるの、と悲鳴のような声で聞かれた。私は曖昧なまま、死のうと思って、と答えた。馬鹿、と頬をはられた後、抱きしめられた。私は、まるでドラマみたいな反応をするんだな、とか、何だか鬱陶しいな、とか考えていた。
母が仕事中の父に電話をしている最中、私はずっと手を握られていた。母は涙声で父と話していた。
しばらくして、父が帰ってきた。仕事を途中で切り上げてきたらしい。父も、私を見るなり手を強く握ってきた。よく分からなかった。
両親が、病院に行こう、と言うので、私は頷いた。面倒だったが、親に捕まえられた以上、逃げることはできないと思った。病院に行っても何が変わるわけでもない、とも思った。
大学病院の精神科ではしばらく待たされた。両親の悲愴な表情が申し訳なかったが、それをどうにかできそうな気も、する気も起きなかった。フコーは常に視界の隅にいて、時々、お前はいるだけ周りを困らせるんだ、死ねばいいんだよ、と言っていた。
診察は、まず一人の男性医師と行われた。ほとんどのことは親が話していた。元々私が集団生活にうまくなじめていなさそうだったこと、高校に入り部活に積極的に参加し始めてよかったと思っていたのに辞めてしまったこと、それから元気がなかったこと、元気になったと思ったら食事中などに時折何もない場所を見つめたり一人で笑顔になったりしていること、そして死のうとしていたこと。恥ずかしく、私の実感とは違うことも多かった。しかし、訂正するのが面倒だし、自分の内面をわざわざ話すのも嫌で、私はただ聞いていた。頷くことも、表情を変えることも、ほとんどしなかったと思う。
それから両親が退席し、私と医師で話した。死にたかったそうですが、どうしてですか、大きな悩みや辛かったことがあったんですか、と聞かれた。姫宮達との関係を説明させられるのも、まして九島さんに迷惑をかけるのも嫌だった。なので、特にはありません、ただ生きると迷惑をかけそうで、とだけ答えた。口にして初めて分かったが、それはただの出まかせではなく、私が昔から持っていた不安でもあった。
普通の人が普通にできることが、私にはできなかった。例えば机の整頓や、他人に合わせる自然な笑顔や、決まった時間に寝て起きることなんかが。アイドルや、ドラマや、将来やりたい仕事みたいな、みんなが興味を持つことに興味を持てなかった。「お前は欠けてるんだよ」。それがどこであれなんであれ、私と同じグループになった人は嫌そうな表情をしている気がした。私が失敗をして足を引っ張った時、舌打ちなんかをされると心が痛かった。笑顔で、大丈夫気にしないから、なんて言われても、その笑顔の裏では顔をしかめているのだろうと思って胸が苦しかった。私はどこに行っても厄介者だと思われている気がした。「実際そうだ」。私に大きな愛情を向け、投資をしてくれている両親に対してさえ、その愛情に全く報いることができなくて、反動で愛情を鬱陶しく思っている。私はどこに行っても、自分がはまらないパズルのピースのように感じていた。いるだけで私は見苦しいのだと感じていた。高校で合唱部に入って、九島さんに会って、それは少し変わったはずだった。でもそれも駄目になった。
……私はそんなことを考えながら、医師の質問に笑顔を作って、適当に答えていた。考えていた自分の不安については伝えなかった。この、医師という肩書を持つらしい知らない人には、助けてほしいとも頼ろうとも思えなかった。
いない人の声が聞こえたりしますか、と聞かれた。私は、いいえ、と笑顔で答えた。親の説明から、私がフコーに反応しているのは明らかだ。つまりこの「いいえ」は、みえみえの嘘、拒絶の嘘になる。ちょうど九島さんに、九島さんを好きになったから部を辞めたんだ、と言ったようなものだ。さすがに医師は怒ったりせず、困ったように微笑んで、そうですか、と言った。
それから医師が三人に増え、私の両親も呼び戻され、六人で面談をした。今までの確認の様な問答の後、医師たちが何か相談した。そして私に、任意入院が勧められた。いわゆる閉鎖病棟、外界と隔絶された空間、そこへの入院。両親はその提案に動揺しているようだったが、私自身は不思議と他人事のように感じられていた。ご両親も心配なさっているようですし、安全な場所でゆっくり休んでもらえるようにという処置です、との医師の説明に、両親は戸惑いつつも頷いた。私は、別にいいですよ、とやはり他人事のように答えた。拒否できるとも思えなかったし、入院した所で何が変わるとも思わなかった。その場で契約書を渡され、流し見てサインをした。父が、「ふたえぇ、戻ってこいよぉ……」と涙声で言っていた。ここにいる私は彼にとって娘ではないのだろうか、と思った。
そして、あっという間に病院側の受け入れ準備が整えられ、私は病室に案内された。
「――大まかな規則は、これくらいですね。あとは自分で読んでおいてください」
「はい」
私は従順に頷いた。噛みつく要素などないのだから当たり前だが。
「それじゃあ、また先生から説明があると思いますから、それまでは休んでいてください」
「はい」
言い残し、看護師は病室を出て行った。
「こんな所にいたって無駄だ」
フコーの声が頭で響く。そうなのだろうか。きっとそうなのだろう。
ベッドに座って私は周囲を見回す。
ベッドが4つ並んでいる、白い部屋。ベッドとベッドの間はカーテンで仕切れるようになっているが、今は開いている。どのベッドも使われているらしい。私の分のベッドの空きがあったのは幸いと言うべきかどうなのか。ベッドの横には、腰ほどの高さのキャスター付きの床頭台。中に物を入れられるようになっていて、机と棚を兼ねる。この床頭台とベッド下の空間が、患者に許された収納スペースなのだろう。窓を見ると、網が入っていていかにもという感じだ。嵌め殺しではないようだが、きっと少ししか開かないのだ。入り口横の壁には、何かとがった物でもぶつけたようなへこみがあった。
見まわしていると、正面のベッドにいる女性と目があった。私は外見で年齢を判断するのは苦手だが、三十代の後半あたりだろうか。浅黒い顔をしている。軽く会釈をすると、彼女は躊躇いがちに口を開いた。
「ど、どうも、はじめまして」
少しどもりがあった。そして、何とはなしに、例えば目線の動き方などに、違和感を感じる。
「新しく、は、入られたんですか」
「ええ、そういうことになりそうです」
「なんで、ですか」
いきなり踏み込んだことを聞くもんだな、と思った。しかし、私はここでいつまでか分からない時間を過ごすのだ。この閉じた環境で。それなら、精一杯人当たりよくしておいた方がいいだろう。私は笑顔(とその時の私は思っていた表情)で答える。
「いやあ、よく分からないんです。ただ、死にたいと思っちゃって」
「ああ……。わ、私も、死にたくって」
流石は精神病棟、自殺願望なんて有り触れているらしい。
「何歳?」
「……十六です」
「若いですねえ。私は、よ、四十二」
その後も、女性は他愛ない会話を続けてきた。誰もが中空を見つめて会話が成立しないようなイメージを閉鎖病棟にはもっていたため、意外だった。ところどころ話題が飛ぶ所はあるが、会話はできている。私のイメージは偏見だったのだろうか。それともこの女性が特に話し好きなのだろうか。
しばらくして、医師からの説明を受けていた両親がやってきた。できる限りいつも通りに接そうと努力しているのが分かって、痛々しかった。私はそれにどう応じればいいのか分からずに、ぼそぼそと、家から持ってきてほしい物を頼んだ。両親はそれを承諾して帰っていった。残された私はセンチメンタルになるかなと思ったが、そんなことはなかった。思考が感情から遊離しているような感覚があった。
向かいの女性がまた話しかけてきた。それをしばらく聞いていると、最初に一人で診察をした医師がやってきた。彼が私の主治医となるらしい。
個室に連れて行かれ、これからのことについて説明を受けた。と言っても、詳しいことは語られず、ゆっくり休んでください、という意味の話をされて病室に戻された。
それから、夕飯を食べたり、他の患者の人と話したりした。食堂やホールなどにいる人たちは、話し好きの傾向があるようだった。この病棟での生活のコツ、例えば医師にあまり後ろ向きなことは言わない方がいいだとか、朝と夕方にホールのタンクに補充されるお茶を自分のペットボトルに汲んでおいたほうがいいだとか、そんな話をされた。誰かの話を聞いていると、フコーの私を責める声から少し気がそれた。相手からすると、私は自分ではほとんど喋らないし、時々頭の中で反響する声に耐えるため黙りこむので、奇妙に感じられたかもしれない。それともこの場所では、そんなこといちいち気にされないのだろうか。
そうこうするうちに、消灯時間の九時近くになった。薬を取りに来てくださいとアナウンスされてナースセンターに行くと、二錠の薬が渡された。睡眠導入剤と安定剤だという。なるほど病院らしくなってきた、と思いながら、その場で水を渡され飲んだ。
ベッドに戻り、病院着に着替えていると、照明が落ちた。廊下の灯りはついたまま、病室の扉は開けっぱなしであり、真っ暗ではない。
ベッドに横になってもなかなか眠くならずに、影の中で白く浮かぶ自分の腕を見ていた。
こんな所に入れられて、これからのことが不安になるはずだよなと思いながら、その感情は湧いてこなかった。
幻聴が聞こえるかという医師の問いに、頷くべきだったろうか。けれど私は、はい、と答えて、フコーがただの幻だと、精神科で治療されるべき病気の症状だと認めるのが嫌だった。
「九島を苦しませておいて、何がゆっくり休むだ?」
フコーの声が響く。フコーは今も私を責める。けれどそれは、私がそうしたいと思っているからだ。フコーは間違ったことを言わない。いぜん変わりなく。
これからどうなるのだろう。分からない。分からないけれど、幸せに生きることはできないと思った。幸せになるには、私は臆病すぎるし、怠惰すぎるし、わがまますぎるし、醜すぎるし、弱すぎるから。
フコーは私を幸せにするために現れたのだということを、信じられる気がした。幸せになるには、死ぬしかないのだ。できる限り静かに、迷惑をかけず、死んでしまいたかった。
「そうだ、そうしろ、早くしろ」
フコーは急かす。けれど、この空間で命を絶つのはひどく難しい。そこまでして死のうという気力がなかった。
「根性無しが、それだから駄目なんだ」
何を考えるのも面倒だった。薬のおかげか眠気がやってきた。そのまま私は意識を手放した。
オーナー:takatei
評価数:5
(elec.)(samantha)(suika)(utsm4)(clown)
どんどん鬱展開 (elec.)(03/24 01時48分18秒)
|